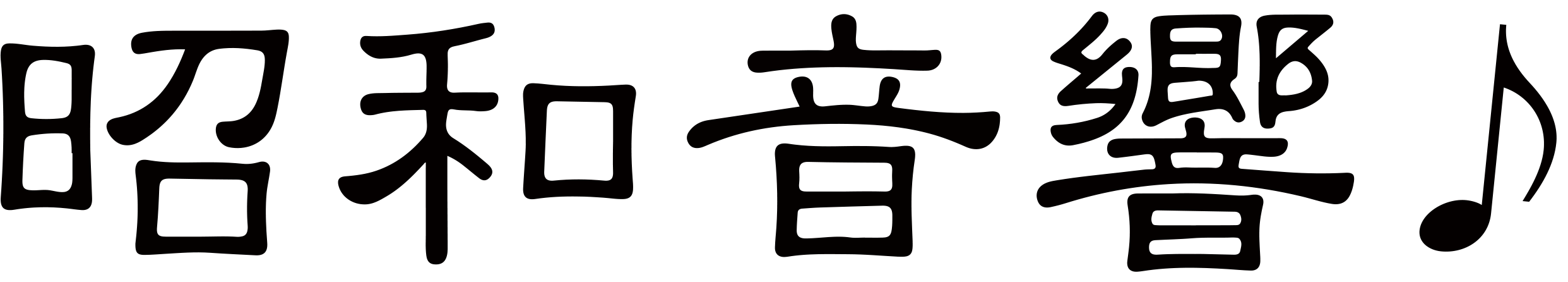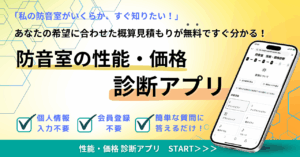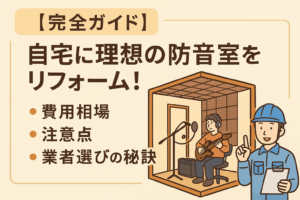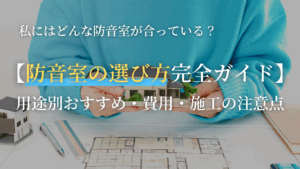ご自宅で、ピアノの練習をするなら、防音対策もしっかりと施すことが大切です。
特にマンションでは、防音対策が遅れてしまい、近隣からのクレームにつながっているケースでご相談を頂く事がよくあります。
昨今はテレワークの導入や、在宅勤務も増加し近隣住人の方の在宅率が高くなり、比例して騒音問題も目立つようになっており、メディアでもよく取り上げられるようになりました。
一度クレームがきてご近所様との関係が悪化すると、その解決にはクレーム発生前よりも大きな負担がかかる事が多いようです。
ご自身の練習頻度にあわせて、適切な防音対策を取り入れると、周囲に気兼ねなく自由気ままに、気の向くままに思いっきりピアノの練習に
励めるようになるでしょう。
この記事では、ピアノの防音対策について説明します。知っておきたい基礎知識とともに、住居タイプ別の効果的な対策を紹介するので、しっかり音漏れを防ぎたいと考える人はぜひ参考にしてください。
防音対策は2つの音を意識して行いましょう
ピアノの防音対策をする場合、音の伝わり方に着目することが大切です。音の伝わり方にはさまざまな特徴があるため、まずはそれらを理解しなければなりません。具体的には、空気伝播音と固体振動音の2つを意識する必要があります。
空気伝播音とは、空気を通して伝わる音のことです。空気には重さがあるため、音による振動が発生すると空気にも振動が伝わって音波が発生します。音波が耳の中にある鼓膜や耳小骨などに伝わることで、人は音が鳴っていると感じます。そのため、音を発する物体と人の間に空気を遮断する物体がある場合、人に空気伝播音が伝わりにくくなります。また、距離が離れていればいるほど音波はさらに届きにくくなるので、空気伝播音も伝わりにくくなります。
一方、固体振動音とは、物から物へ伝わる音のことです。物体の振動により音が伝わっていくので、触れ合っている物体を介してどんどん遠くへ広がっていきます。建物の中であれば床や壁などを通して響きながら他の部屋へ音が伝わるため、音を感じてもどこから鳴っているのか把握しにくいです。そのため、固体振動音を感じると、たとえそれほど大きな音でなくても気になります。
建物の中での音の伝わり方は、木造や鉄筋コンクリートなどの構造の違いによっても変化します。ただし、音が伝わるのを防ぐ施工をおこなえば、構造の基本的な性質以上に音を伝えにくくすることも可能です。空気伝播音と固体振動音の両方を抑える工夫を取り入れましょう。
ピアノの防音対策で重要なこと



ピアノの防音対策をする場合、具体的にどのようなことをおこなえばいいのでしょうか。できる限り音が伝わらないようにするには、壁、窓、床のそれぞれについて対策を取り入れる必要があります。少しでも対策が不十分な箇所があると、その部分から部屋の外に音が伝わってしまう可能性があるので注意が必要です。
ここでは、壁、窓、床のそれぞれについて、ピアノの防音対策において押さえておきたい重要なポイントを詳しく紹介します。
壁の対策
壁の防音対策をするには、吸音効果と遮音効果のある部材を使用します。具体的には、グラスウールと面密度の高い建材を使用すると効果的です。グラスウールとはリサイクルされたガラスを原料としており、遠心力をかけて繊維状にした素材です。グラスウールは断熱材として使用されることも多いですが、吸音材としても高い効果を発揮します。
一方、面密度の高い建材には遮音性があり、重量に応じてその効果は高くなります。グラスウールと建材を使用して防音対策を施せば、室内で発生した音を壁でしっかりと止めることが可能です。グラスウールで音を吸音し、面密度の高い建材でその音の遮蔽するようなイメージです。
ネット通販でも防音壁や吸音パネルもあるので、それらを使用すれば壁の音漏れ対策が強化できるでしょう。
窓の対策
窓はガラスでできていて壁や床よりも薄いため、建物の中では最も音が外へ伝わりやすい部分です。そのため、窓には特に念入りに防音対策を施す必要があります。
たとえば、すでについている窓の内側にもう1つ窓を取り付ける方法があります。二重サッシにすることにより窓と窓の間に空気の層ができるため、家の中の音が外に漏れるのを防止する効果を高められます。また、吸音素材でできたカーテンを使用すれば、防音対策の強化も可能です。この場合、ピアノをひくときは窓とカーテンの両方を閉めるようにしてください。
より高い防音の効果を得たいなら、追加の窓ではなく防音壁をはめ込むというのもひとつの手です。
ただし、窓をすべてふさぐ必要があるため、窓から光を取り込めなくなるので要注意です。窓に防音壁を設置するなら、部屋の明るさをどのように確保するか事前に検討しておいたほうがいいでしょう。
床の対策
鍵盤を叩いたりペダルを踏んだりする際の床衝撃音が床に伝わって広がるため、ピアノを演奏するなら床の防音対策も重要です。たとえ弱い力で演奏していても、床衝撃音は必ず床へ伝わってしまいます。万が一、床の対策を忘れると、下の階にいる人にとって騒音となる可能性が高いので注意しましょう。床から音が漏れるのを防ぐには、建物に振動音が伝わる前に減衰させるのが重要です。
そのため、床の防音対策としては、振動を抑える防振材や緩衝材を敷くと効果的です。柔らかい素材でできているため、床衝撃音による振動も多少吸収して建物に伝わる振動を緩和できます。ゴムマットについて言うと市販品でもサイズも豊富なので、ピアノのサイズに合わせて設置できる点も便利です。
インテリアにもこだわりたい場合は、カーペットを敷くのもおすすめです。カラーバリエーションやデザインにたくさんの種類があるため、部屋の雰囲気に合わせて好きなものを選べます。厚みも幅広く用意されているため、より分厚いものを選ぶと二次的に吸音の効果も期待できるでしょう。
住居タイプ別のピアノ防音対策と費用



しっかりと防音するには、それぞれの状況に合わせた効果的な対策が必要です。そのため、戸建やマンションといった住居のタイプの違いによっても、取り入れるべき防音対策は変化します。費用についてもそれぞれに違いがあるので注意が必要です。それぞれの住居でしっかりと防音したい場合、どのような対策をおこなえばいいのでしょうか。ここでは、戸建の場合とマンションの場合のそれぞれについて、具体的な防音対策と費用を紹介します。
戸建の場合
戸建の場合、ピアノの音漏れを防ぐための防音工事をおこなうには6帖程度で約2週間程かかります。
事前にお約束したスケジュールに沿って工事を進めます。
浮き構造による防振性能が担保された防音室では、固体伝播音が軽減できるため、演奏によって生じる振動を建物の躯体に伝えにくく
できます。結果として、高い遮音性が得られ、周囲に音が漏れる心配をしっかりと抑える効果を期待できます。
工事では単に音を遮断するだけでなく、ピアノの鳴りや響きを活かせるような環境の整備が可能です。防音の性能を高めながら、室内全体の
音の響きを調整する工事は、防音業者の中でもさらに専門性が高い一部の業者にしか設計施工できない技術です。
工事は6帖程度で約250万円程から依頼できます。ほとんどの業者はご希望やご予算に合わせてオーダーメイドでご対応してもらえるので
まずは実際に相談してみるといいでしょう。
昭和音響に無料お見積りをご相談の方はこちらをクリックしてくださいhttps://www.showaonkyo.com/contact/
マンションの場合
マンションでも防音工事は基本的に可能です。ただし、稀に状況によっては工事の実施が難しいケースもあります。
例をあげると、タワーマンションの高層階では、部材が重すぎて重量オーバーとなったりする可能性もあります。
マンションの防音室は、木造住宅とは異なり大スパンの空間の中で、自由にレイアウトを変える事ができるのがメリットでしょう。
リフォームなので、スケルトン工事は必要となりますが、好きな広さで防音室を作る事ができるのが利点です。また、コンクリートの持つ
もともとの遮音性能の高さから、複合遮音性能では高い防音が得られやすいです。
最近は、防音室を完備した防音マンションも多くできてきました。
防音マンションの価格は、完成時期、立地、部屋の大きさなどの条件によって異なりますが、本格的な防音マンションであれば自分専用の
練習空間としてセカンドハウスで賃貸されるのも良いかもしれません。
昭和音響施工の防音マンション ⇒ https://www.showaonkyo.com/2022/12/29/shinka-apartment/
ピアノの防音対策 まとめ
音は空気伝播音や固体伝播音として周囲に広がっていくため、それらの特徴に合わせた防音対策が必要です。室内でピアノを演奏すれば、窓、壁、床、天井を通じて室外へ漏れていきます。そのため、それぞれについて音による振動を遮断する対策を取り入れるのが重要なポイントとなります。
建物の構造や住居のタイプに合わせて対策するなら、専門業者に依頼すると確実です。ピアノの防音については、建築音響の一級建築士事務所「昭和音響♪」に相談してみるのがおすすめです。それぞれの状況に合わせてプランを作成するので、必要な対策をしっかり施すことができます。適切な防音対策をうまく取り入れつつ、ピアノの練習がしやすい環境を手に入れましょう。
お問合せはこちらから https://www.showaonkyo.com/contact/
また以下ページにて施工例も掲載しております。
https://www.showaonkyo.com/sekozirei.html